
 原稿制作に寄せられる小説代筆のご依頼は多岐にわたります。
原稿制作に寄せられる小説代筆のご依頼は多岐にわたります。
長年温めたアイデアをカタチにしたい。ブランディングのために自著を持ちたい。書き貯めた作品を整理して一冊の本にしたい……等々。
原稿制作はこれまでにたくさんのお望みを叶え、ご好評いただいてまいりました。
持ち込まれるアイデアはどのようなスタイルでも構いません。
書きかけの原稿、筋書のみ、設定のみ。お渡し方法は紙でもデータでも対面取材でもOK。
原稿制作の代表ライターがご依頼者様のアイデアを整理し、物語の構成を提案します。ご納得いただいて執筆を開始です。
原稿制作はゴーストライターに徹し、作品の情報を一切漏らしません。テキスト生成AIが現状実現できていない日本語のハイコンテクスト性を活かした作品づくりをお約束します。
可能な限り対応させていただきます。よろしければ懸案中の企画をご開示ください。

以下の流れはあくまでも基本形です。ご依頼者様のご要望に応じて柔軟に対応いたします。






「原稿制作」の原稿料は、作業の総量を20×20原稿用紙枚数に換算して計算します。
原稿用紙単価は、ご提供いただける情報、またはご依頼内容によって異なります。
※ 価格は消費税10%を含みます。
※ グループサイト「さくら文研」と同一の価格基準を採り入れています。
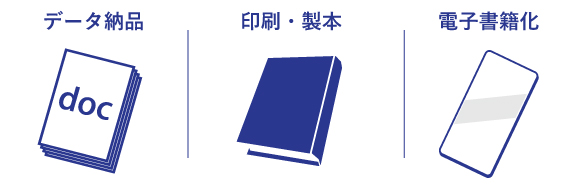
ご依頼の原稿はお客様のご希望のスタイルでご納品いたします。
原稿のデータはマイクロソフトワードのファイル形式にて全てのお客様にお納めします。
ご要望に応じて印刷製本・電子書籍化(epubファイル生成)等も承ります。
装丁デザインや挿絵・図表の制作もお任せください。
製本した際のページ数ごとに、文字数・原稿用紙換算枚数・原稿料金の目安をまとめてみました。執筆料金の詳細は【原稿料金】のページをご確認ください。
判型ごとの文字数は、以下の数値を基本としています。
四六判:15行×40文字(占有率75%)
A5:16行×45文字(占有率70%)
※ 印刷・製本、出張取材の際の取材費・交通費等は別途です。お問い合わせください。
※ 表は正味の原稿のみを計算しています。実際の製本では本文以外に、目次・扉・章ごとの改ページ・奥付などが加わります。

原稿制作は2010年発足の『小説代理原稿連合会』(現在は終了)に端を発する文章作成代行サービスです。培った経験と蓄積したノウハウでご依頼者様のご希望どおりの執筆と印刷製本を行います。
原稿作成前の構成案のご提案および本原稿の執筆では、ご依頼者様のご意向・ご希望を最優先します。
事実の解釈や表現について、どしどしご意見をください。また、迷いがある時はご遠慮なくお申し付けください。細心のご提案をいたします。
原稿料はグループサイト規定により変動はなく常に明朗です。
印刷・製本は原油価格や紙資源相場により若干の変動がありますが、お見積の際に明朗にご提示いたします。
参考価格
原稿制作で代筆する全ての原稿は、原稿完成後に当方より原稿料ご請求後、ご入金確認を以って納品となり、作品の権利がご依頼者様のものとなります。
その後、ご依頼者様が文章を書き足しても、削っても、売り出してヒットしても、ご依頼者様固有の事情です。原稿制作が関連性を公開することはなく、印刷製本した場合でも、奥付に記名いたしません(印刷所の名前は載ります)。

当方で小説を作成してくださったご依頼者様のお声を2つご案内いたします。

一姫二太郎は育てやすいと聞いたことがありますが、わが家の小学校4年と2年生は元気いっぱい、毎日台風のような日々です。手を焼きながらも、この子たちが育つ未来が楽しみでなりません。しかし、この子たちもいつかは聞き分けの良い大人になり、私は年老いていつまでも母性の喜びを味わえるわけではありません。
今の私のメンタリティで、未来の子供たちに伝えたいことはないか――忙中にも筆を執り、なんらか書き綴ろうとするものの、うまくいかず。原稿制作さんに意図を伝えて原稿を作成してもらいました。小説にしたのはご提案を受けたからです。こむずかしい読み物よりも、フィクションにした方が読みやすいとのすすめで、納得できる作品を作っていただきました。
海外 W様 30代

少年時代、山腹のわが屋のそばに廃墟になった礼拝堂があり、仲間と夜な夜な忍び込んでは、あれは幽霊だ、狐憑きだと騒いで、世の神秘をたずねたものです。その思い出がいくつになっても懐かしく、一篇の物語にならないものかと考えているうちに、齢50を超え、当時一緒に忍び込んだ仲間の何人かは早くも泉下の人となりました。
原稿制作さんに小説にしてもらうにあたり、友人の設定には私のこだわりを極力活かしてもらいました。小説というものは可能な限り登場人物を減らすのがよいらしいのですが、私は当時の友人を全員登場させたかった。みなに活躍のシーンを作りたかった。全部を実現してもらいました。かけがえのない一冊です。
長崎県 K様 50代
このほかにも多数のお言葉をいただいています。グループサイト「さくら作文研究所」のWEBサイトに小説・自分史作成のご依頼者様のロングインタビューを収録しています。該当ページをご覧ください。
☞【ご依頼者様ロングインタビュー 】
】
自分史作成インタビュー①
実際の雰囲気が分かる−半小説半自伝の依頼
※ グループサイト「さくら作文研究所」の作成動画です。
☞【さくら文研Youtube ch 】
】

創業以来数々の小説代筆に携わってまいりました。個人法人を問わず、私小説・文芸作品・広報的役割の著述まで、幅広くお手伝いしています。
ゴーストライターをお探しの方の中には「大丈夫かな?」「任せられるかな?」と疑問を抱かれる方も多いでしょう。
まずはその不安をまるごとお話しください。
様々なご依頼を通して培ったノウハウで疑念を払拭し、必ずご満足いただける作品作りをお約束します。

言うまでもなく「筆力」ですが、その意味するところは広範で、「企画力・構成力・文章力」など様々な力が含まれます。この他にも、小説を書くために必要な洞察、すなわち、社会への関心や哲学的考え方といった人文学の素養も必要となります。筆力にそれらをプラスした力は「総合力」と呼ぶべきものです。
小説とは、複雑な構成物です。著者は広大な世界からモチーフを選び、展開させ、結末を付けます。複数のファクトを配置し、連結させ、ひとまとまりに仕上げます。この技術は著者が積み上げてきた技術と経験に委ねられているわけですが、これを裏付けるのが総合力です。
専門馬鹿という言葉がありますが、小説の場合、専門的だと視野狭窄が起こります。ジャンルは作品の可動域を制限します。著者の可能性も狭めるのです。
病院の例えが分かりやすいでしょう。
昨今の病院は、無数の専門科に分かれています。ある人が肩が痛くて整形外科に通いましたが、リハビリばかりで治りません。
放置していたら体調が悪化し、精密検査の結果肝臓がんだと分かりました。
のちのち「総合病院にかかっていれば」「肩こりが内臓と関係するなんて気づかなかった」と後悔した……そんな話を耳にしたことがあります。
複雑につながった構造である人体を断片的に分析することは木を見て森を見ない典型のごとき話です。
専門性にのめりこむと、このように全体を見失うことになります。
原稿制作は、多様なご依頼を通じ、経験値を積み上げてきました。ぜひお話しを聞かせていただきたいと思います。
よい小説とは何か。答えは明快で「読者の感慨を誘う作品」であることです。
「最後まで読んでもらえる」「読者に意図したとおりの印象を残す」といったことも、それに含まれます。
もっとも、これは小説に限らず、どんな読み物にも言えます。コンセプト至上主義や構造論(起承転結など)、テーマやレトリックも同様です。特に小説には「総合力」が必要ですから、大切でないものなどないのです。
小説の場合、特に「モチーフとその増幅のプロセス」が重要です。
一つの個性的な設定(モチーフ)で読者の関心を引き付け、物語の進行にそって様々に変化(増幅させる)させて面白さや深みを生み、オチでうまく結ぶ、というはたらきです。
国民的コミック『ドラえもん』を例にとりましょう。
はじめに設定として「便利な道具を持っている未来の猫型ロボット」というモチーフがあります。
モチーフの繰り出す未来の道具が物語を二転三転させ(これが「増幅プロセス」です)、最後は道具から離れない範囲でオチを結実。
視聴者は「ああ、おもしろかった!」と満足します。これがドラえもん的構造論です。
増幅プロセスの表現には「緊張と緩和」「カタルシス醸成」など物語技法がありますが、これらはストーリーありきのテクニックですので、やはり根本はモチーフであると思います。
ウソ(フィクション)と承知で読ませる小説ですから、面白いウソでなければ価値はなく、人は貴重な時間を割いてまで手に取って読んくれません。
いかにモチーフを使いこなしておもしろくするかが作成の勘所となります。

モチーフの選定はお客様との綿密なやりとりが不可欠です。
お客様はご依頼にあたり、作品を一定の段階に仕立てられています。その仕上がり具合は様々です。
モチーフがお決まりの方もいれば、漠然としてる方もあり、未定の方もあります。
どのケースであれ、私はお客様が小説を通じて何をおっしゃりたいかをうかがい(コンセプト)、モチーフを企画し、それをいかに展開させ物語として成立させるかを提案いたします。
ご依頼にあたっては、まずは思いのたけをお伝えください。
「どんなテーマを、どんなふうに、誰に読ませたいか」
お客様のイメージを最大限に増幅し、豊かな物語をつくるお手伝いをいたします。
>>文例集へ
>>料 金へ
>>お問い合わせへ